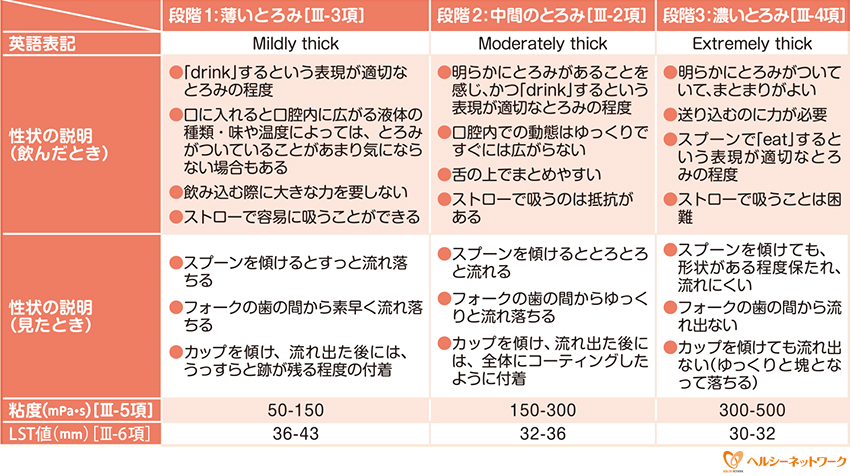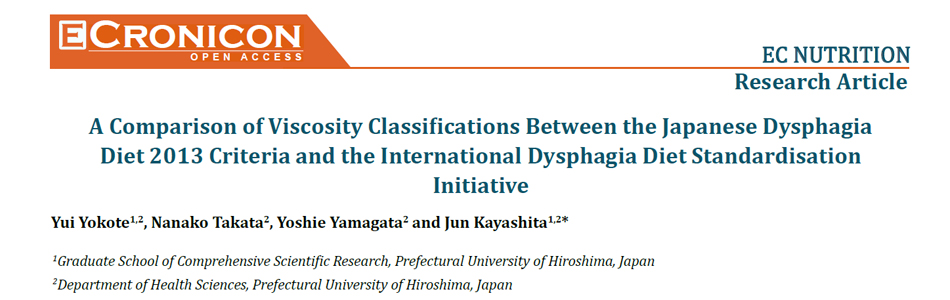日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌に論文が掲載されました。
この論文は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2013(以下、学会分類2013)のとろみの各段階(薄いとろみ,中間のとろみ,濃いとろみ)の粘度範囲を決定した官能評価の結果をまとめたものです。
山縣誉志江, 與儀沙織, 栢下淳
官能評価による学会分類2013(とろみ)の粘度範囲の妥当性
日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌, 21, 129-135, 2017.
前報(宇山理沙,藤谷順子,大越ひろ,栢下淳,前田広士,小城明子,高橋浩二,藤島一郎:とろみ液の官能評価による分類 粘度およびLine Spread Test値の範囲設定,日摂食嚥下リハ会誌,18, 13-21, 2014.)と併せてお読みいただければ、この粘度範囲となった経緯をご理解いただけるかと思います。
*************************************
とろみ剤を使用される際は、この学会分類2013(とろみ)をひとつのめやすとしていただけたらよいかと思います。
学会分類2013(とろみ)早見表
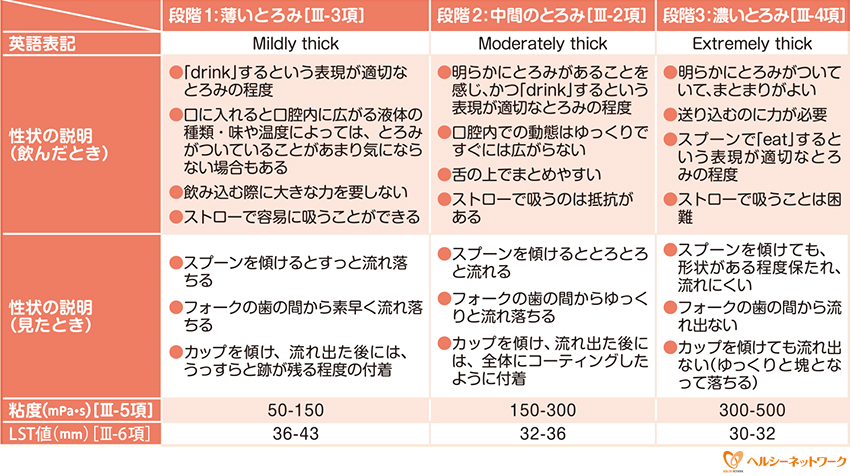
本表は必ず「嚥下調整食分類2013」の本文を併せてお読みください。
なお、本表中の[ ]表示は、本文中の該当箇所を指します。
粘度:コーンプレート型回転粘度計を用い、測定温度20℃、ずり速度50s-1における1分後の粘度測定結果[Ⅲ-5項]。
LST値:ラインスプレッドテスト用プラスチック測定板を用いて内径30mmの金属製リングに試料を20ml注入し、30秒後にリングを持ち上げ、30秒後に試料の広がり距離を6点測定し、その平均値をLST値とする[Ⅲ-6項]。
ヘルシーフード社サイト「栄養指導NAVI」より
では、ご使用になられているとろみ剤の場合、何%で使用すれば、どの段階になるのでしょうか。
本研究室では、とろみ剤を「標準タイプ」と「少量高粘度タイプ」に分類し、それぞれのとろみ剤を何%で使用すれば学会分類2013(とろみ)の各段階に相当する粘度になるのかを報告しています(下表)。
|
商品名 |
販売元 |
使用目安量(g)/水100 mlあたり |
薄い
とろみ |
中間の
とろみ |
濃い
とろみ |
|
少量
高粘度
タイプ
|
トロメリンV |
ニュートリー |
0.6~0.9 |
0.9~1.4 |
1.4~1.9 |
| ネオハイトロミールⅢ |
フードケア |
0.4~0.8 |
0.8~1.4 |
1.4~2.1 |
| トロミパワースマイル |
ヘルシーフード |
0.5~1.0 |
1.0~1.6 |
1.6~2.4 |
| トロミアップパーフェクト |
日清オイリオグループ |
0.5~1.0 |
1.0~1.7 |
1.7~2.4 |
| トロメリンEx |
ニュートリー |
0.6~1.1 |
1.1~1.9 |
1.9~2.6 |
標準
タイプ |
トロミクリア |
ヘルシーフード |
0.5~1.1 |
1.1~2.0 |
2.0~2.9 |
| 明治トロメイクSP |
明治 |
0.5~1.2 |
1.2~2.1 |
2.1~2.7 |
| トロミスマイル |
ヘルシーフード |
0.6~1.2 |
1.2~2.0 |
2.0~3.1 |
| 新スルーキングi |
キッセイ薬品工業 |
0.6~1.3 |
1.3~2.2 |
2.2~3.4 |
| ネオハイトロミールR&E |
フードケア |
0.6~1.4 |
1.4~2.2 |
2.2~3.2 |
| ソフティアS |
ニュートリー |
0.7~1.4 |
1.4~2.3 |
2.3~3.2 |
| つるりんこQuickly |
クリニコ |
0.8~1.6 |
1.6~2.6 |
2.6~3.3 |
「少量高粘度タイプ」では文字通り、「標準タイプ」に比べ、少量の添加で強くとろみがつく傾向にあります。
これら以外にも、様々なとろみ剤があります(下表)。
使用されているとろみ剤が「少量高粘度タイプ」に分類されるかどうかは、知っておくことで添加し過ぎの防止につながります。標準タイプと比較し、少量の添加量の違いでも粘度が変化しやすいですので、計量には十分に気をつけていただけたらと思います。
|
商品名 |
販売元 |
少量高粘度
タイプ |
トロメイクコンパクト |
明治 |
| ソフティアSUPER S |
ニュートリー |
| つるりんこpowerfull |
クリニコ |
| 標準タイプ |
トロミファイン |
キユーピー |
| トロメイククリア |
明治 |
| ネオハイトロミールスリム |
フードケア |
| トロミアップエース |
日清オイリオグループ |
| ソフティア1 |
ニュートリー |
| スルーソフトQ |
キッセイ薬品工業 |
| スルーマイルド |
キッセイ薬品工業 |
| ネオハイトロミールNEXT |
フードケア |
| おうちで簡単トロメイク |
明治 |
たくさんのとろみ剤があり、選択に迷われるかもしれませんが、市場に出回っているこれらキサンタンガム系のとろみ剤は、少量高粘度タイプか否かを除けば、特別注意を要する大きな違いはなく、良い製品が多いと感じます。
製品により、価格が安い、ダマにならず溶けやすい、早くとろみがつくなどのコンセプトがあるかと思いますので、ご自身のニーズに合ったものを使用されてみてはいかがでしょうか。
※ ふたつの表のとろみ剤の掲載順は、論文をもとに作成しています。
※ これらの分類は、ある一定の粘度で線引きしたもので、あくまで目安です。使用の際には、実際のとろみの強さをご確認ください。